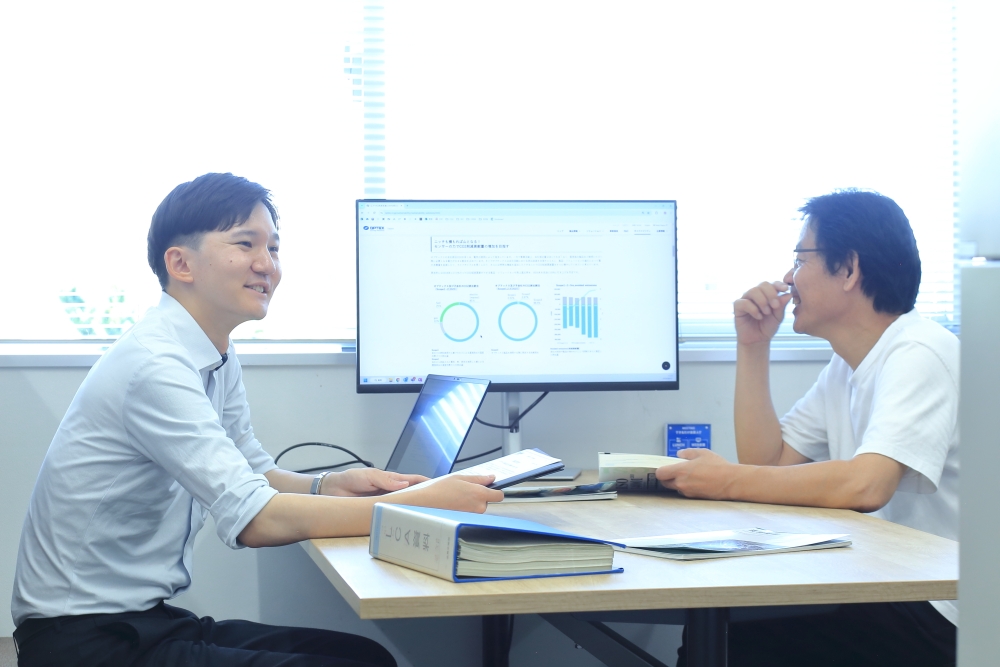Interview
Vol.007
親子みたいな二人に聞く
企業と環境のサステナビリティ
秀さん 松井 楽幸
Hide-san, Motoyuki Matsui
- 1997年
- 秀さん(33歳) オプテックスに入社
松井 (0歳) 富山県にて誕生
- 2009年
- 秀さん(45歳) オプテックスで環境事務局の担当になる
松井(11歳) 地元サッカーチーム、カターレ富山にハマる。スポーツ観戦が生活の一部に
- 2017年
- 松井(19歳) レストランでバイトをしながら軽音サークルに所属
- 2020年
- 秀さん(56歳) 内部監査事務局も担当することに
松井(22歳) 京都の会社に入社
- 2023年
- 秀さん(59歳) 還暦を迎え新しいスタート。松井さんと一緒に仕事をするようになる
松井(25歳) オプテックス入社
- 2024年
- 秀さん(60歳) かつてギター好きだった経験を活かし、学生時代の友と音楽活動を開始
親子みたいな二人に聞く
企業と環境のサステナビリティ
品質管理本部 品質統括課 秀さん 松井 楽幸
編集の岡井です。今回は品質管理部門でサステナビリティを担当する方々にスポットライトをあてます。秀さん(仮名)は現在再雇用。松井さんは中途入社したばかりニューカマー。二人の環境に関わるお仕事と業務の継承をテーマに、「環境」のサステナビリティと「企業」のサステナビリティ、その双方についてご紹介します。


Okai
本日はよろしくお願いします。
最初にお二人が所属する品質管理本部について教えてください。

Hide-san
品質管理本部は、製品の品質保証(自社の製品が規定の品質を満たしているかを確認し、納品後もお客様に安心や満足を保証するための活動)と、品質管理(お客様が求める品質を安定的に維持する)全般を担っている部門です。
その中でも「ISOマネジメントシステムの維持管理」と、「環境分野の管理」を任されているのが私たちです。

Matsui
具体的には私と秀さんでISO9001(品質)、ISO14001(環境)のマネジメントシステム維持管理のため、外部認証機関の審査対応や内部監査、マネジメントレビューなどの事務局を担当しています。また製品に関わる化学物質の管理も行っており、各国の規制対応を常に監視し、大きな動向があれば速やかに対処しています。
他にも世界的な気候変動対応の一環として、製品や企業活動により排出される温室効果ガスの算定と情報開示も担っています。

Okai
今のサステナビリティ関連のお仕事に就かれるまでに、どのような経験をされてきたのですか?

Hide-san
前職から品質管理を担当していました。京都の部品メーカーだったのですけれど、そこではお客様の要求の高さに驚いたのを覚えています。お客様にとっては自社の完成品に不具合が出てしまっているわけですから、まさにクレーム地獄でした。この状況からどうやったら脱出できるのか?と、勉強しながらあがいていましたね。
その後縁あってオプテックスに入社し、同じく品質管理を担当しましたが、当時は人や製品に厳しすぎる雰囲気はなかったです。製品不具合があった際の対応も「こんな優しくされていいの?」って思うこともありました。それが33歳の時。

Matsui
僕はその頃0歳。何の記憶もありません。

Hide-san
笑 その後会社の成長に呼応するように、オプテックスのレベルがグングン上がってきて、「真に品質を良くしないといけない!」というムードになりました。特に誰かがやろうとしたわけではなくて、会社中からそんな声が聞こえて来たように記憶しています。
そのような品質管理の「素敵なターニングポイント」を味わったのですが、それとは別に2009年頃に環境対応を管理する事務局を任されまして、ほとんど知識がなかったので、正直に申し上げてこれが重たかった。

Okai
2009年というと京都議定書の削減目標に対する進捗が、多くのメディアで取り上げられていたように思います。

Hide-san
はい。いわゆる業務部門や家庭部門での省エネ対策ですね。当時は紙を節約するためにパソコンで見ましょうとか、モノは買いすぎないようにとか、基本的な取り組みがほとんどでした。しかし「環境」と一言でいっても、色々な課題とアプローチがあることを学びました。
オプテックスは既にISO14001を取っていたので、ゼロからスタートするという動きではなく、環境保護の重要性を啓蒙することから始めました。植樹祭のイベントを行うなどして、会社全体を「環境に振り向かせてやろう!」という気概で活動したのを覚えています。
2009年の植樹祭。娘さんと参加する秀さんの姿も。環境教育教室の講師としても活躍していた。

Matsui
環境問題に企業も取り組んでいかないといけないよ。という土壌をつくったわけですね。私の世代でいうと、「エコ」は幼稚園や小学校のころから身近にありました。むしろちゃんと教わったかどうかも覚えてないくらい当たり前でしたね。デジタルネイティブならぬ、環境ネイティブです。

Hide-san
環境の担当になってから3年間、休みの日には必ず環境教室に通って知識を身に着け、必要だと思われる情報を会社に展開していました。
それまでは車で通勤していたんですけど、事務局がこれではいけないと思い立って電車通勤に切り替えました。当時はハイブリッド車や電気自動車という選択肢もなかったですしね。最初のころは雨の日がつらかったです笑
でも今も電車通勤。かれこれ15年間です。

Okai
そして2023年。松井さんが入社されます。

Matsui
私も転職組なのですが、前職はメーカーのサービス部門を担う企業に所属していて、ISO事務局を担当していました。ISO9001(品質)、ISO14001(環境)、ISO45001(労働安全衛生)の維持管理業務、外部審査対応や内部監査の事務局などを担当し、社員に向けた教育も行っていました。
他には含有化学物質の調査依頼に対する、社内窓口や実際の調査業務も経験しました。オプテックスの実務でも似たような対応を行っています。

Okai
業界は違ってもスムーズに移行できたのでしょうか。

Matsui
はい。オプテックスに入って驚いたのが、ISOマネジメントシステムの運用が驚くほど安定していたことです。以前の経験では、マニュアルや手順への適合性チェックや、不適合への是正処置にかける労力がものすごく大きかった。世間では、「ISOのための仕事」が沢山ある企業の話をよく聞きます。でもオプテックスに来たら、ISOに関する苦労ごとが全然ない。

Hide-san
品質面を例にすると、オプテックスが「真に品質を良くしないといけない」と思い始めた時代から、品質やプロセスの改善意識をずっと持ち続けてきました。そして長年かけて「品質とはこうあるべきだ!」に辿り着いたんです。そして答え合わせにISO9001を使ってみたら、チェックの内容とオプテックスの運用が合致していた。無理に合わせにいってないから、維持しやすいんです。

Matsui
すごいなぁ。ISOのための仕事っていうのが多かれ少なかれ出てしまうものだと思っていたのですが、仕組みとしてちゃんと回っているので。

Hide-san
逆に松井さんはISOの管理課題や運用にすごく詳しかったので、教え込むことも無くスムーズに仲間に加わってくれました。外から来た方、しかもISOに明るい人に「安定している」と言われるとやっぱり嬉しいですね。今の状態は、僕ら先人の微力を何年にもわたって積み重ねた結果だから。

Matsui
実は前職経験から、オプテックスで是正できそうな事項を予測して「カイゼンしまくってやるぞー!」と意気込んで入社したんです。……正直肩透かしですよ笑
今は焦らず、ゆっくり、でも確実に良くしていきたいと思っています。

Okai
現在のオプテックスの環境関連業務についても教えてください。今では企業の社会的責任、環境貢献活動や情報開示が必須とされる時代になりましたね。

Hide-san
全てのステークホルダーさんが、環境貢献無くして企業は存続できないとおっしゃるくらいになりました。だからできていることを伝え、できていないことは補う。世の中のトレンドをいち早く捕まえて対応することが大切だと思っています。

Okai
2024年にCDP※の評価で昨年気候変動のカテゴリーでA-(リーダーシップを発揮)を獲得しました。
※Carbon Disclosure Project(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)から始まった取り組み。現在は脱酸素以外にも幅広く環境インパクトに関するデータを収集し、投資家や政策決定者に提供している。

Matsui
中堅企業としてはかなり高いレベルにあると思います。しかしCDPに提出していることは、会社の環境活動の一部にすぎないんですね。聞かれたことに答えているだけで、実際には書いていないことも沢山やっている。だからCDPを介した開示のために何かやっているわけではなくて、お客様のために対応すべき点をつまびらかにし、開示するためのツールとして捉えています。

Hide-san
一番の意味は我々がどこのポジションにあるかを知れることにあるんです。CDPの設問内容や評価は、世界でのオプテックスの位置を確認できるものになっていますから。
オプテックスは海外子会社を含むグループ全体で、太陽光パネルの自社内設置などの温室効果ガス排出削減に取り組む

Hide-san
一方で、我々は自社施設への太陽光パネルの設置や、環境に貢献できる製品の貢献量(削減貢献量)を算出することなど、環境に関わること全体に向けて取り組んでいます。他社や競合に負けないようにやることはもちろん、逆にどこに、どこまでコストをかけるのが最適なのかも冷静に判断しなければならない。
環境に負荷をかけないということに関しては、オプテックスはかなり前から取り組んできました。企業としてやらなければならないことは一通りやり続けているんです。開発の視点も小型・軽量・省エネの製品を作ることにとっくに辿り着いていますし、自社の温室効果ガスの排出削減でいうと、もう絞り出すことしかできないんです。しかし現代はモノからコトへ移行してきています。
コト貢献の一つとして、オプテックスの製品をお使いいただく、他社の温室効果ガスの排出削減に貢献する製品量を増やしていきたいと考えています。

Okai
製品としては無駄開き防止で空調効率を上げる自動ドアセンサーや、センサーライトのLED照明化などですね。
お二人は今後、環境負荷を低減するために活動するのですか?

Hide-san
環境に貢献するために全て最新の材料や技術を使うと非常に高価になります。でも、それは三方良しではないですよね。だから自分たちのポジションや役割を把握して、適切な投資をする必要があるんです。
つまり僕たちは経営判断のための指標を作り、提案していくことがミッションだと思っています。

Matsui
はい。そのために最新情報を常にインプットしています。
また環境を扱う部署にとって琵琶湖の畔というロケーションも特別ですよね。琵琶湖で環境学習を受けている子供たちを見ていると、使命感や責任感を感じやすいです。次世代のためにも誠実に取り組んでいかないとなって。

Okai
お仕事の継承も行われていると思いますが、どのように進められていますか?

Hide-san
さっきも言った通りお互いの考えているスコープが合っていて、既に十二分に仕事してくれていますから。分担もあり、共同もあり。もう何年も前から仕事やってきている感じですよ笑

Matsui
いや、まだそこまでではないですよ!進めていくうえで、業務が多岐に渡るので分担しつつ、どうしてもわからないところとか、知りえないところはサポートのお陰で進められていると思います。ありがたいことに「これはどうしようもないぞ」と困ってしまうことはないですね。

Matsui
本部長の前川さんには、「松井さんはオプテックスがカーボンニュートラルを達成するであろう2050年に、まだ会社にいるからなー!」ってプレッシャーをかけられているんです笑
でも私自身も2050年をリアルに想像しながら、ミッションを引き継いでいかないといけないと思っています。

Hide-san
年齢でいうとほぼ息子ですから。引き続き、一つ屋根の下でうまく連携していければと思っています。
僕はリタイアまであとほんの僅かです。これまで環境活動を一人でやってきましたが、松井さんがいる今が一番いい状態だと思ってる。
でもやっぱり「モノづくりのオプテックス」なんですよ。ISOシステムの維持管理や化学物質管理、環境貢献活動はしっかりやっていっていただけるのは間違いないでしょう。オプテックスの実力もしっかりアピールしてくれると思います。でも本物のモノづくりに対しても携わって欲しいと考えています。そうでないと「表面的な情報」を発信するだけに留まってしまうのではないかと。
だから僕が並走できる限られた時間の中で、品質管理を少し経験してもらいたいな。オプテックスのモノづくりを真に理解して、その上で環境のドキュメントも書くことができる。これこそが、オプテックスの環境担当なんだぞって思っています。

Okai
それは松井さんという人物にとっても差別化になりますね。

Hide-san
今後の環境貢献の大切さを、モノづくりをしている人にも理解してもらいやすくなると思いますし、社会への開示内容もよりリアリティのあるものになるでしょう。

Matsui
ISOや環境貢献活動って確かに表面的にでも推進できるんです。でも頭で分かっているだけに留まってしまう。これじゃあモノづくりやサービスの本質には到達できていないよな。というのは今までの経験でまさに感じていたことでした。
でも自分は頭でっかちの「環境オジサン」にはなりたくないんです!

Hide-san
そうならないよう自分が会社にいる間に、出来る限りのコツや技を松井さんに伝えていきたいと思っています。
師弟ですか?いや、そういう上下な感じではなくて、得意分野が違う同僚としてです。

Okai
最後にさきほどお話しにあがった「2050年にカーボンニュートラル実現」という指標について、意気込みを聞かせてください。

Hide-san
2050年。きっと今では想像ができない色々なことができるようになっているでしょうね。だから時代に応じて、まったく新しい対応だってできるはず。今は不安もあると思いますが、「カーボンニュートラルはできる!」って胸を張っていればいいんですよ!

Matsui
はい、しっかりやっていきます。
2050年になって、ああ「秀さんの言ってたこと、間違ってなかったな~」って思い返せたら嬉しいですね。
オプテックスの企業存続の裏には、徹底した品質管理や環境へのこだわりが確かにありました。そして、それは秀さんから松井さんへと、有限の時間の中で受け継がれていきます。持続可能な環境の実現には長い年月がかかるからこそ、組織として意志を持ち続けることが重要です。秀さんの熱が途切れず続いていく様を嬉しく思いつつ、2050年の答え合わせを楽しみにしたいと思います。
企画・編集:岡井良文
ご意見・ご感想がございましたら、お気軽にお寄せください。
※本記事は2024年11月時点の取材内容で構成しています。